「厄年」とは
「厄年」とは、人生の節目に様々な体調の変化があるので気をつけるようにとの戒めの意味が込められているもの。
厄年の年齢は、基本的に男女別に考えられています。
ですが、完全に年齢が別になっているわけでもありません。
男女共通の厄年というものもあります。
また、年齢は数え年で見ていきます。
現在、私たちが使っている年齢とは違います。数え年の場合、母親のお腹にいる月日も命と考えますので、生まれた年は0歳ではなく、1歳になります。
男の厄年
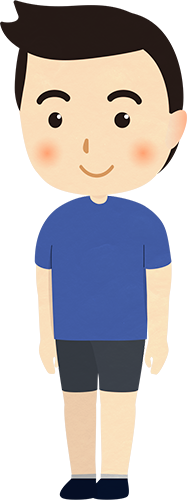
男の厄年は、数え年で25歳、42歳、61歳とされています。特に42歳は大厄と言われていて、最も注意しなければならない年齢と言われています。
厄年の前後3年は注意しなければいけません。
昔は人生50年と言われていた時代で、42歳と言えばもう晩年を迎えた年齢でした。
厄年になると、「役」につき、神社の経営や祭事執行に関係することを許され、地域を取り仕切ることもある年齢でしたが、体のあちこちにも不調が出て来る頃です。
実際、現代の42歳と言えば働き盛りですが、仕事でも無理をしがちです。
やはり健康に変化が訪れやすい年齢とも言われていますので、大厄には注意が必要です。
女の厄年
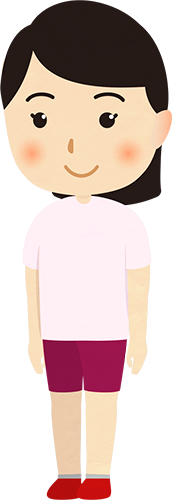
女の厄年は、19歳、33歳、37歳と言われています。
大厄は33歳で、男性同様、前後の3年間は注意しなければいけません。
33歳は「散々」に通じるものがあるからだともいわれていますが、これは語呂合わせに過ぎず、やはり人生の節目として、節度のある生活を送ることが大切です。
女性の場合は、妊娠や出産に関わるものもあり、19歳の厄年はちょうど卵巣の機能が安定する頃で、妊娠機能が整います。
次にピークを迎えるのが33歳の大厄の頃です。
この年齢でしたら、子育てで大変な思いをしているお母さんもいるでしょう。
次の厄年にあたる37歳は、高齢出産にさしかかる年齢です。
こうしてみると、体の変化に伴って、厄年がやってくるのが分かります。
30歳を過ぎたら、乳がんや子宮系の病気にも注意しなければいけませんので、厄落としの意味も込めて、健康診断を受けるのもいいですね。
「前厄」と「後厄」
厄年の前後各1年も注意しなければいけない年とされています。厄年の前の1年は、厄の前兆が現れる年齢として前厄と呼ばれ、本厄を迎えたのち、厄が薄らいでいく年として、後厄がやってきます。
ですから、本厄を挟んで全部で3年は注意しなければいけないということになります。
反対に、前厄で注意を払っていれば、本厄で大きなこともなく過ごせ、油断しないで後厄を過ごすことによって、大事に至らないということです。
大きな厄年は、年齢が男女別に分けられていますが、男女共通の厄年もあります。
30歳まで:1歳 、3歳 、7歳 、10歳 、13歳 、24歳 、28歳
30~60歳:46歳 、49歳 、52歳 、55歳 、60歳
60歳から:64歳 、70歳 、73歳 、77歳 、82歳 、88歳 、91歳
とされています。
この中に、男女別の年齢が厄年として入ることになります。
また、結婚している人は、相手が大厄の年齢になると、自分が小厄になってしまいますので、人生のほとんどが厄年ということになってしまいます。
男女別の厄年しか知らない人も多いですよね。
そして厄年を気にする人も多いでしょう。
厄年に関する説

厄年に関しては、いろいろな説があります。
一番語られている説は、一生のうちで一番災難に遭うおそれが多い年だと言われています。
一生のうちで最も危険な大厄は、男は42歳(しに)、女は33歳(さんざん)の歳です。
実際、女性の場合、33歳の厄年に、婦人科系の病気になる人が多く、また離婚率も、厄年に当たる31~33歳が高くなっています。
男性の場合、大厄42歳前後は、大腸ガンや咽頭ガンの発生率が高くなっています。
また厄年の災難は、自分だけでなく周りにふりかかることもあります。
親や子どもに災難がふりかかることもあるようなので、できることなら厄払いはしておいたほうがいいです。厄払いをしておけば、気分的に落ち着き、災難がふりかからないよう意識して行動するようになると思いますので。


