次代へ遺す、想いを伝える「遺言書を作る」
遺言書とは

遺言書。
それはあなたからご家族のために、最後に残せる思いやり。
遺産分割や相続を執り行うことは、悲しみにくれるご遺族にとって、大変な負担を伴いますが、遺言書にはその負担を軽くしてあげる力があります。
「遺言なんて一部の資産家のためだけのもの」。
そんな考えは過去のものとなり、今では前向きに遺言書を作成される方が増えています。
あなたも、もめない円滑な相続のためにお元気なうちから、急がずゆっくり、遺言書作成について考えてみませんか?
あなたの遺言書必要度は?セルフチェックリスト

「自分には財産もそんなにないし、遺言書なんて必要あるのかしら?」そういう迷いのある方が多いと思います。
遺言書必要度のチェックリストを作ってみましたので、一度、ご自身でセルフチェックしてみませんか?
法定遺言には2種類あります。

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、作成手順も死後の手続きも異なります。それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。
「自筆証書遺言の場合」
①財産と相続人把握し、誰に何を残すか決める
②自分で書く
・手軽に無料で作成でき、内容を知られずに済む
③自分で保管しておく
④死亡
⑤遺族が家庭裁判所に申し立て
・遺族が勝手に開封することはできません(最大5万円の過料に処せらます)
・相続人全員の戸籍謄本などを準備する
⑥家裁にて開封および検認(偽造・変造されていないかの確認)
・法的に無効な遺言書であった場合は、検認を受けても遺言は有効になりません
⑦相続手続きへ
・手続き開始までに約2~3か月
「公正証書遺言場合」
①財産と相続人把握し、誰に何を残すか決める
・印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本などを準備する
②公証役場で作成
・証人二人と相続額に応じた手数料が必要
③原本を公証役場に保管(正本は遺言者の手元へ)
・ご家族に「公証役場で遺言書を作成してある」と生前に伝えておくと安心
④死亡
・ご遺族が遺言書の存在を確認できる「公正証書遺言検索システム」も利用可能
⑤検認不用(すぐに相続手続き可能)
当事務所としては、公正証書遺言をお勧めします。
その理由は、
①書式不備の恐れがなく、遺言が無効になる心配がない
②原本が公証役場に保管されているので、紛失の恐れがない
③偽造・変造の恐れがない
④検認の必要がなく、すぐに相続手続きが開始できる
(検認は、相続人全員の戸籍謄本の取り寄せなどが必要でかなりの手間がかかります。)
知っておきたい遺言書作成の基礎知識(遺言を確実に実行してくれる「遺言執行者」は誰に頼むべき?)
遺言者ご本人が亡くなったあと、遺言書の内容に従って実際に財産副分けを取り仕切る人が「遺言執行者」です。法律上、必ず遺言執行者を定めなければならないわけではありませんが、確実にあなたの思いを実行してもらうためにも、遺言執行者を定めて遺言書に書き記しておくことをおすすめします。
ただし、遺言執行者の仕事は、財産調査から不動産の名義変更手続きまでの多岐に渡り非常に複雑です。
財産によっては、何十枚、何百枚の書類に目を通して署名する必要もありますので、その負担も含めて誰に依頼するかをよく検討したほうが良いでしょう。
その点、相続手続きの専門家である司法書士を遺言執行者にご指名いだければ、面倒な手続きも確実に早く行えますので安心です。
知っておきたい遺言書作成の基礎知識(遺言書の意外な盲点、「遺留分」をお忘れなく)

遺留分とは、被相続人が相続人に対して「最低限度残さないといけない遺産」のことです。遺留分の割合は被相続人と相続人の間柄によって決まります。
これによって、例えば「法定相続人のう長男だけに財産を相続する」や「愛人に全財産を遺贈する」などといった遺言によって生じる、極端な配分を防ぐことが出来ます。
遺留分を無視し遺言書であっても、遺言が無効になるわけではありませんが、侵害された相続人は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内、相続開始から10年以内に「遺留分減殺請求」を行うことで、遺留分を確保することができます。
このようなもめごとを避けるにも、遺言書を作る場合は、遺留分を忘れずに考慮しておきましょう。
また、相当程度の生前贈与をする代わりに遺留分放棄を依頼する方法もあります。
知っておきたい遺言書作成の基礎知識(遺言の存在、家族にどう知らせる?保管はどうする?)
せっかく書いた遺言書も、亡くなった後に誰かに見つけてもらわなければ、あなたの遺志を伝えることはできません。遺言書が見つからなければ、遺産分割協議によって、あなたの思いは異なる遺産分配をされてしまうでしょう。
遺言書を残されるのなら生前から遺言書の存在を知らせておきましょう。
ただ、保管の方法には注意が必要です。あまり厳重に保管されると発見されにくく、また、誰でも目に付くところに置いておくと、自筆証書遺言の場合、偽造や変造をされる危険性があります。
また、遺言書の存在がオープンになりすぎると、かえって家族の争いのもとになる場合もあるかもしれませんので、信頼できる親族や第三者に遺言書の存在と保管場所を伝えておき、自分の死亡後に相続人や遺贈をしたい人に伝えてもらうようお願いしておくのも一案です。
知っておきたい遺言書作成の基礎知識(遺言は何度でも書き直せます。気負わず書き始めてみては。)
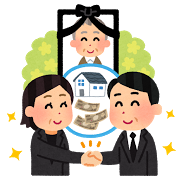
生きている間は、すでに書いた遺言書の内容を変更したり、撤回することが可能です。自筆証書遺言書ならば
一番簡単な方法は古い遺言書を破棄して新しい遺言書を作成することです。
訂正を行うこともできますが、法律的に難しいルールがあり、訂正の方法を間違うと無効になる場合がありますので、新しい遺言書を作成したほうが確実です。
公正証書遺言の場合は、遺言書の原本が交証役場に保管されているため、新しい遺言書を作成しないと、先に書いた遺言書を撤回したことになりません。
新旧2通の遺言書の作成方式は、必ずしも同じである必要はなく、自筆証書遺言から公正証書遺言へと変更することもできます。
遺言書が複数ある場合は、最新の日付のものが有効となります。
古い遺言書の全てが無効になるのではなく、新旧で内容が抵触する部分についてのみ最新の遺言書が有効となります。
一度遺言書を書けばその内容に拘束されるというわけではありませんので、老いへの備えのひとつの形と考えて、元気なうちに気楽に遺言書を書いてみましょう。


